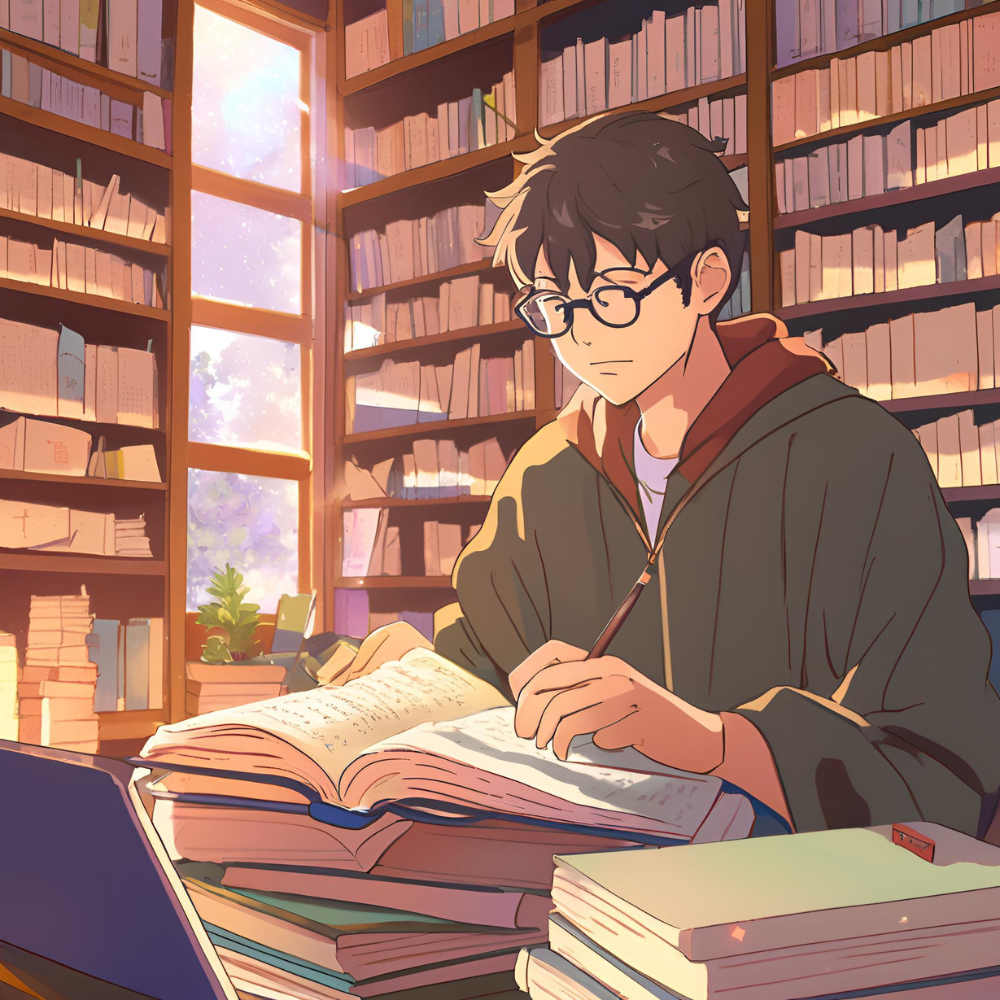最近、新たな据え置き型娯楽端末を導入し、余暇時間の過ごし方に一層の彩りを添えられるようになった佐野です。
今回は7月から実施している「GRANDIT」研修について、概要を説明します。
また、研修を通じて新人に修得してほしいと考えられている技能を考察します。
GRANDIT研修の概要
GRANDIT研修では、設計書をもとにしたカスタマイズ課題を行っています。
複数の課題が課され、設計書どおりの実装を行う訓練をしています。
各課題は、製造→単体テスト→レビュー
の流れとなっています。
また、後半の課題ではこれに加えて単体テスト仕様書の作成も行っています。
各フェーズについて
製造
製造では、まずカスタマイズの概要に目を通し、その後詳細設計書を確認します。
そして、適宜ドキュメントを参照しながらコーディングを行います。
本工程では、主に3つの技能を養うことが求められていると考えます。
1つ目は、設計書を読み解く力です。
詳細設計書はコーディング可能なレベルまで詳細に仕様が記述された文書ですが、文面だけでは意図が十分に伝わらない場合があり、行間を読む力が求められることがあります。
例として、「○○から△△を取得して××に設定する」のような記述があった場合、「○○から△△を取得する処理」と「××に△△を設定する処理」の2つを実装しなければならないと考えます。
しかし、前者は標準で既に実装済みで、実際には後者の処理のみ実装すればよいなどのことがあります。
また、設計書に誤りが含まれる場合もあるため、設計書を盲信せず常に懐疑的な視点で確認しながら読むことも必要であると感じました。
2つ目は、コーディング力です。
コーディングは製造のメインですが、単にコードを記述するだけでなく、保守性を考慮することが求められます。
3つ目は、GRANDITでの実装方法の理解です。
カスタマイズ課題では、標準の実装方法をまねて製造することが多いです。
実装しようとしている処理が、GRANDITではどのように実装されているか学ぶことが大切だと感じています。
単体テスト仕様書作成
単体テスト仕様書作成では過不足なくテスト項目を洗い出すことが求められますが、それには2つの技能が要求されると考えます。
1つ目は、仕様詳細からテスト項目を抜き出す力です。
テスト項目は設計書の仕様詳細をもとにして作成します。
実装したイベントが正しく動作するか確認するための条件などを考えます。
2つ目は、影響範囲を特定する力です。
カスタマイズにより変更を加えた部分は、すべてテストしてバグの有無を確認しなければなりません。
よって、設計書の仕様詳細には書かれていない部分にカスタマイズによる影響が出る可能性がある場合、当該項目もテストに含めなくてはなりません。それゆえ、影響範囲を見極める能力が必要と考えます。
単体テスト
単体テスト仕様書のテスト項目に対してエビデンスを取得し、正しく動作することを証明します。
また、不具合があれば修正して再度テストを行い、バグをなくしていきます。
本工程では、正しくエビデンスを取得する力が求められていると考えます。
例として、更新処理の場合は更新前と更新後の両方の画面キャプチャを取得するなど、どのようなエビデンスであれば正しく動作していることを証明できるか見極める力が必要であると考えます。
レビュー
各課題が終了したら、チューターの方にレビューをお願いしています。
レビューでは、コード、動作、単体テスト仕様書、単体テストをチェックしていただいています。
製造中に出た疑問を解消し、コードの理解を深める場となっています。
最後に
GRANDIT研修も終わりが近づき、案件に配属される日がいよいよ近くなってきました。
これまで学んだことを実務に活かしていきたいです。